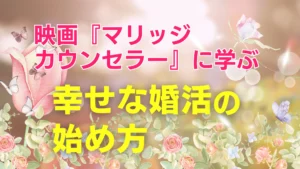学資保険×NISA×児童手当で教育費の最適化を目指す

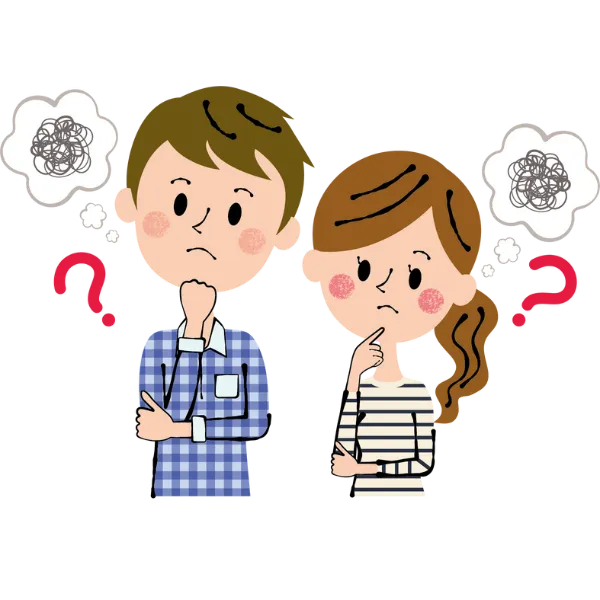
教育費の準備に悩む夫婦
「学資保険とNISAって、どっちがいいのかな? 児童手当はどう活用すべき? 物価がどんどん高くなってるけど、大学費用の準備はどうすればいいんだろ…?」
「子どもの将来のために何か始めたいけど、何から手をつけていいか分からない…」そんな声に寄り添いながら、今回は教育費のリアルと対策をやさしく解説します。
教育費の疑問や不安は、これから出産を控えるご夫婦や子育て中の方から本当によく寄せられます。
「毎月の予算は限られている」「万一の保障も欲しい」「でもお金も増やしたい」——この“全部大事”をどう両立するかが難しいですよね。
「学資保険 × NISA × 児童手当」で教育費を最短・最適化する具体戦略(35歳夫婦・【第1子】来年/【第2子】再来年想定)
本記事では、学資保険の“確実性と保障”、NISAの“非課税×成長性”、そして児童手当の“公的原資”という三本柱をどう組み合わせれば、18年後の大学費用を過不足なく用意できるのかを、モデル数値と配分例まで踏み込んで解説します。
記事を書いている私は、埼玉県川越市のIBJ加盟相談所『マリッジコンシェルジュ Sweet Color』で婚活カウンセラーを務めると同時に、FP2級として家計設計・教育費計画のご相談にも日常的に携わっています。
実際のご夫婦のケースに基づいた現実的な配分比率・商品選びの考え方・リスクの捉え方を、専門用語を使わずにわかりやすくお届けします。
この記事を読み進めるだけで、「何をどれくらい・いつから積み立てればよいか」がクリアになり、インフレや万一の事態にもブレない設計が自分たちで判断できるようになります。
「迷って動けない時間」を今日で終わらせ、最初の一歩を“正しい順番”で踏み出すための実践ガイドとしてご活用ください。
目次
第1章:教育費の現実と、35歳夫婦が感じるお金の不安

子どもが生まれると、誰もがふと立ち止まって考えます。
「この子の将来のために、いくら貯めておけば安心なんだろう?」と。
文部科学省の調査によると、子ども1人にかかる教育費は、すべて公立でも950万円前後。大学まで私立に通うと、2,000万円を超えるケースもあります。
こうした数字を見ると、「とても自分たちには…」と不安になる方も多いでしょう。
ただ、ここで知ってほしいのは、教育費は「一度に払うものではない」ということ。幼稚園から大学まで、18年間にわたって少しずつ必要になるお金です。
だからこそ、焦らず「計画的に準備していく仕組み」を作ることが大切なんです。

私自身も、第一子の出産を控えたときに「教育費って現実的にどう貯めるのがベストなんだろう?」と悩みました。考えれば考えるほど焦る気持ち、とてもよく分かります。
ここからは、実際に多くの家庭が取り入れている3つの教育資金の柱を整理しながら、どんな組み合わせが無理なく続けられるのかを一緒に考えていきましょう。
第2章:「学資保険」で安心を確保する

まず、多くの家庭が最初に検討するのが「学資保険」。
これは教育費を積み立てるための“貯蓄型保険”です。一定期間、毎月保険料を支払い、子どもの成長に合わせて祝い金や満期金を受け取ります。
特徴は、「強制的に貯まる仕組み」であること。
途中で引き出せない分、確実に教育資金を確保できます。さらに、契約者(親)に万一のことがあった際は、その後の保険料が免除され、予定通りの満期金を受け取れるのも大きな安心です。
例えばフコク生命の「みらいのつばさ」では、15年間で180万円払込し、200万円の満期金を受け取れるケースも。返戻率は110%前後で、銀行預金よりも効率的に貯められます。

学資保険は“貯める力よりも守る力”。インフレには弱い面もありますが、確実にお金を残すという意味でとても優秀です。特に共働き世帯では、安心材料として1本入れておくのがおすすめです。
ただし注意点もあります。途中解約すると元本割れすること、インフレ時には実質価値が目減りすること。この2点を理解しておくと、後悔しない選択ができます。
第3章:「NISA」で教育費を“育てる”

次に注目したいのが「NISA(ニーサ)」。
投資信託や株式などの運用益が非課税になる制度です。
NISAは、長期でコツコツ積み立てる家庭にぴったり。
毎月1万円を年利3%で18年間積み立てると、総額約286万円。元本216万円に対して70万円の利益が見込めます。 もちろん、相場によっては一時的にマイナスになる年もありますが、長期的にはプラスに転じる可能性が高いです。

NISAは“育てるお金”。投資って最初は怖いかもしれませんが、5年10年と時間を味方にすると、学資保険では届かない増やす力を発揮します。僕自身もNISAで教育費の一部を運用しています。
ただし、NISAは「元本保証がない」ことを忘れずに。
短期ではなく、10年以上の長期視点でコツコツ積み立てるのがポイントです。
「増やす部分はNISA」「守る部分は学資保険」と役割を分けておくと、バランスの良い教育資金づくりができます。
第4章:児童手当を“第三の柱”にする

そして忘れてはいけないのが「児童手当」。
2024年度からは支給期間が「高校3年生の年度末」まで拡大され、0〜3歳は月15,000円、3歳〜18歳は月10,000円が支給されます。0歳から18歳までの受給合計は、子ども1人につき約234万円!
学資保険とNISAを合わせて積み立てるだけでなく、児童手当を“使わずに貯める”ことで、教育費の大半をまかなうことも可能なんです。
Sweet Colorでライフプラン相談を受けたご夫婦の中には、児童手当を丸ごとNISAに回し、大学進学時に約350万円を確保できたケースもあります。
この具体的な制度の仕組みや活用方法は、 『児童手当が高校生まで拡大!FPが最新制度を徹底解説』で詳しく解説しています。

児童手当は“国からもらえる教育資金”。生活費に混ぜず、別口座で育てることがポイントです。貯めるだけでも、大学費用の半分は準備できますよ。
学資保険で守り、NISAで育て、児童手当で支える。
この3つを上手に組み合わせれば、18年後の教育資金に不安はなくなります。
「将来が漠然と不安」「お金のことは苦手」という方も大丈夫。
仕組みを一度理解すれば、あとは自動的に積み上がっていきます。
第5章:配分比率と商品選び、リスクの考え方
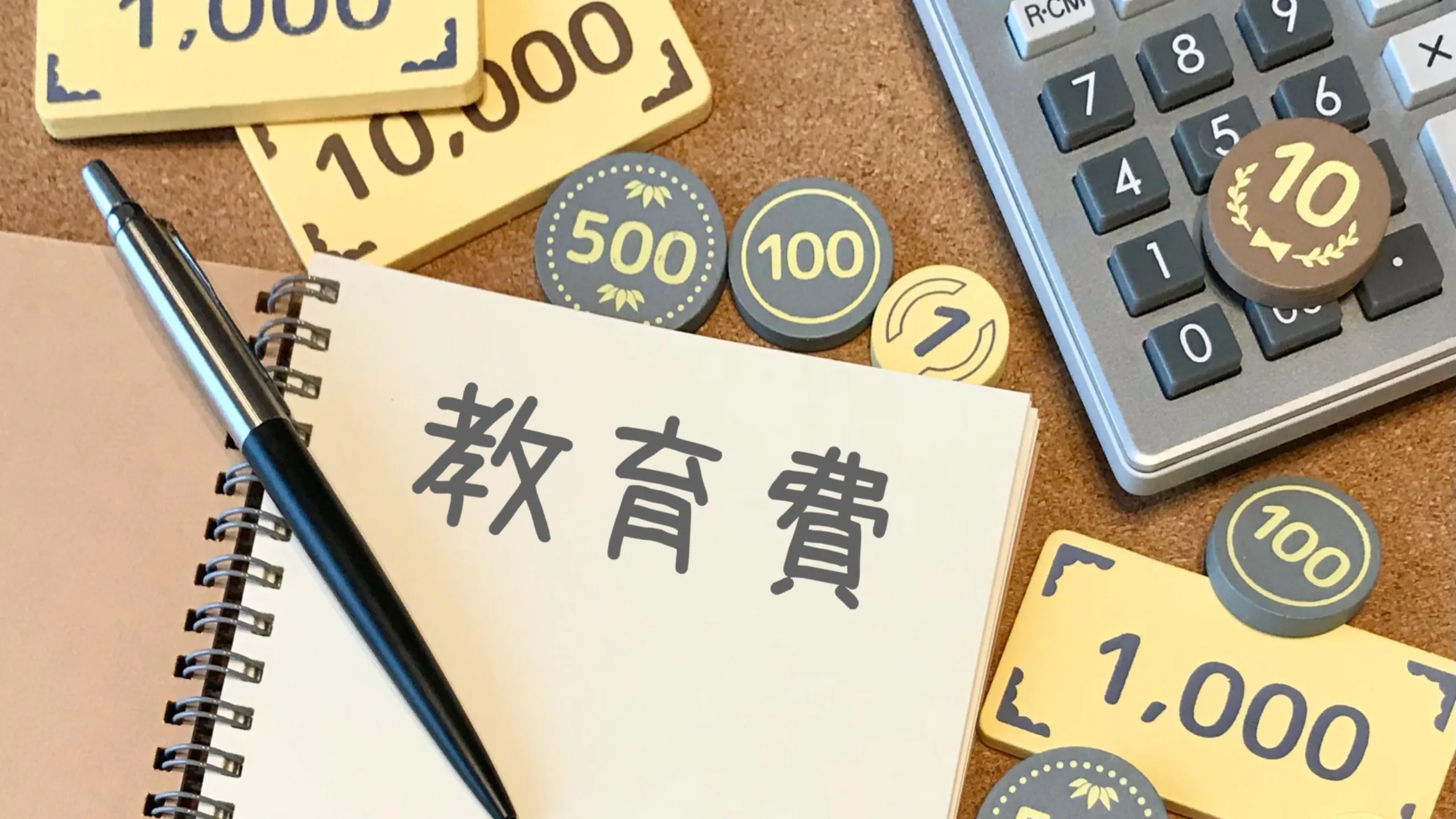
ここで、多くの方が気になるのが「結局、どのくらい・いつから・どう分けて貯めればいいの?」という具体的な部分です。
毎月の予算が3万円あった場合、私のおすすめは以下のような比率です。
- 学資保険:1.5万円(確実に貯める)
- NISA:1万円(長期で増やす)
- 予備口座または児童手当積立:0.5万円(柔軟に対応)
この組み合わせなら、教育費を「守りながら増やす」バランスが取れます。
商品選びのコツはシンプルです。
・学資保険は返戻率100%以上を目安に。
・NISAは全世界株式やS&P500など、分散されたインデックス型を選ぶ。
・短期で引き出す予定のないお金を優先的に投資に回す。
この3点を押さえれば、細かい知識がなくても安心です。
18年間の積立結果(毎月:学資1.5万円/NISA1万円/積立0.5万円)
【前提】期間:18年(216か月)
- 学資保険:月15,000円・返戻率110%
- NISA:月10,000円・年利3%(月次複利・概算)
- 積立(無リスク想定):月5,000円(利息なし)
① 学資保険
毎月:15,000円 × 216か月
積立元本:3,240,000円
満期受取(110%):3,564,000円
元本超過分:+324,000円
② NISA(年利3%想定)
毎月:10,000円 × 216か月
積立元本:2,160,000円
将来評価額:2,859,403円
運用益(概算):+699,403円
※計算式:1万円×{[(1+0.03/12)216−1]÷(0.03/12)}
③ 積立(利息なし)
毎月:5,000円 × 216か月
最終額(=元本):1,080,000円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 積立総元本(3本合計) | 6,480,000円 |
| 18年後の推定最終額 | 7,503,403円 |
| 元本超過分(増えた額) | +1,023,403円 |
(参考)NISA利回りの比較
| 想定年利 | NISA将来評価額 | 合計最終額(3本合計) |
|---|---|---|
| 年2% | 2,597,400円 | 7,241,400円 |
| 年3%(基準) | 2,859,403円 | 7,503,403円 |
| 年4% | 3,155,924円 | 7,799,924円 |
※NISAの将来評価額は市場環境により上下します。上記は一定利回りでの概算例です。
FP所見:学資保険は「確実に+10%」の守り、NISAは「非課税×複利」の育てる力、積立は「流動性の確保」。3本柱の組み合わせで、インフレや万一にもブレにくい設計になります。
※児童手当(子ども1人あたり約234万円目安)を“使わず貯める”を重ねると、大学初年度の一時費用にも余裕が生まれます。

教育費は「守る・増やす・備える」をどう分けるかが鍵です。大事なのは“完璧を目指さないこと”。できる額から始めて、仕組み化するのが長続きのコツですよ。
リスクの捉え方も重要です。
NISAは値動きがあるぶん不安に感じるかもしれませんが、「時間を味方にする」ことでリスクは自然と分散されます。
たとえば、毎月一定額を18年積み立てれば、過去データ上でも平均リターンは年3%前後。
焦らず続けることが最大のリスク回避になります。
このように配分・商品選び・リスク理解の3つを押さえると、「何をどれくらい・いつから積み立てるか」が自然と見えてきます。 迷わず動ける設計を、自分たちで判断できるようになります。
まとめ:教育費は「守る・育てる・支える」の3本柱で安心設計を
教育費の準備に「正解」はありませんが、行動を早く始めた人ほど不安が小さくなるのは確かです。
学資保険で“確実に貯め”、NISAで“お金を育て”、児童手当で“国の支援を活かす”——この3つの流れを押さえれば、将来の教育費はしっかりと備えられます。
今すぐ大きな金額を動かす必要はありません。まずは毎月の予算の中で、「貯める仕組み」をつくることから。
時間を味方につければ、18年後には確かな安心が積み上がっていきます。
「自分たちの収入やライフプランに合った最適な配分を知りたい」という方は、ぜひ気軽にご相談ください。
FPの視点から、無理なく続けられる形を一緒に考えましょう。