教育資金はNISA?学資保険?迷う夫婦へFPの答え
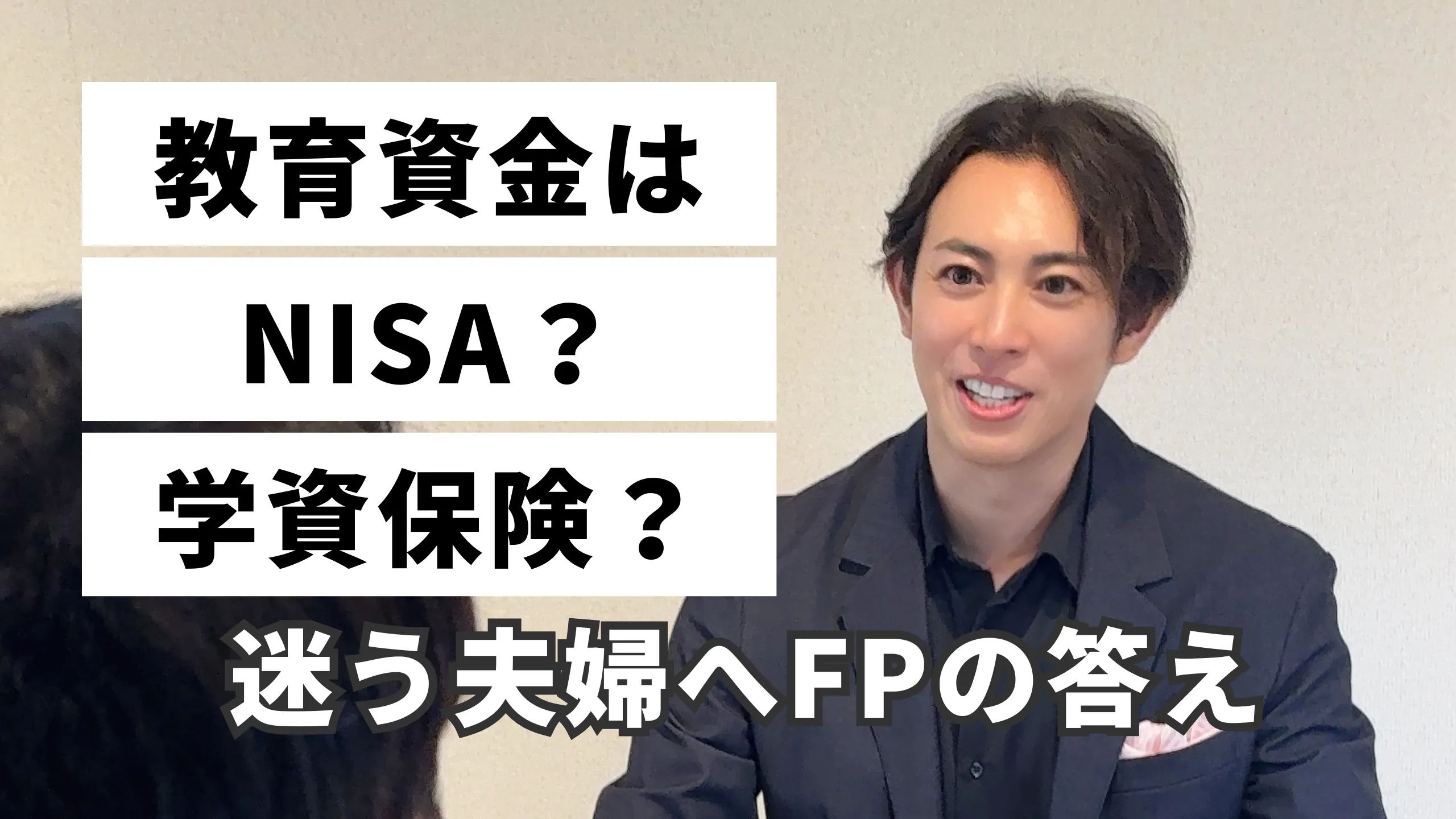
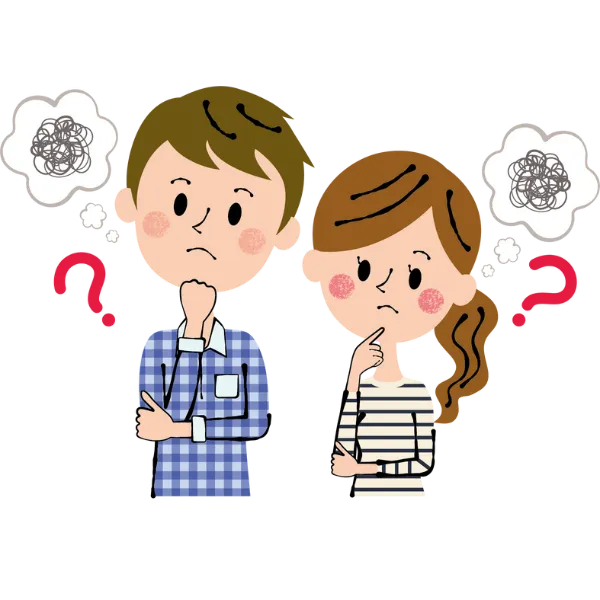
結婚を控えたカップル
「子どもが生まれたら、教育費ってどのくらいかかるんだろう…? どうやって貯めるのが正解?」
教育費は多くの家庭で「想像よりも負担が大きい」と感じるテーマです。 文部科学省の調査によると、幼稚園から高校までの学費だけで公立約600万円・私立約1,980万円。 さらに大学進学まで含めると、合計で1,000万円以上に達することも珍しくありません。
これだけの金額をどう準備すればいいのか——。 昔ながらの学資保険か、それとも最近人気のNISA(ニーサ)での積立投資か。 悩むカップルはとても多いです。
「学資保険とNISA、どちらで教育資金を貯めるべき?」FPカウンセラーが本音で解説します
この記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)資格を持つ婚活カウンセラーの視点から、 教育資金を「安心して」「効率よく」貯める方法をわかりやすく紹介します。
学資保険とNISAの仕組みや違い、返戻率を高めるコツ、さらに2025年現在のおすすめ商品まで、 FPとしての実体験も交えながら丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、「自分たちに合ったお金の貯め方」が明確になり、 結婚後のライフプランを安心して描けるようになるはずです。
目次
第1章 子どもができたら気になる「教育資金」、どうやって貯める?

結婚が決まり、新しい生活が始まると、少しずつ将来の話をする時間が増えていきますよね。
「子どもができたら、教育費ってどのくらいかかるのかな?」
そんな会話をされたことはありませんか?
実際、文部科学省の調査によると、幼稚園3歳から高校卒業までの15年間にかかる教育費の平均は、 公立で約600万円、私立だと約1,980万円。
大学4年間の入学料、授業料等の合計は、国公立で約250万円、私立文系で約410万円、私立理系で約540万円となっています。 出典:文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査の結果について」
文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
この金額、どうやって準備すればいいのでしょうか。
昔から定番なのは学資保険です。
でも最近では、「NISAで運用して貯める方がいいのでは?」という声も増えています。
どちらが正解なんでしょうか…

FP相談でも「どっちがいいの?」と聞かれることが多いです。結論は、家庭毎の目的や性格によって答えは変わります。
第2章 学資保険の安心とNISAの成長力、その違いを知ろう

学資保険は、貯蓄と保障がセットになった保険商品です。
毎月決まった金額を積み立て、契約者(親)にもしものことがあった場合は、以後の保険料は免除。予定通りの学資金が支払われます。
学資保険は、いわば「守りの貯蓄」。リスクが少なく、確実に貯められる安心感が魅力です。
返戻率はおおよそ102〜108%が目安です。最近は金利上昇もあり、返戻率は少しずつ上向きになっています。
一方でNISAは「攻めの資産形成」。投資による売却益が非課税で、長期運用により資産形成を図ることができます。
例えば、毎月3万円を18年間、年4%で運用できた場合、約960万円になります。
元本648万円に対して、約310万円の利益です。
つまり、リスクはあるけど増える可能性も大きい。これがNISAの強みです。

「確実に貯めたい」なら学資保険。「リスク覚悟で増やしたい」ならNISA。どちらを選ぶかは性格にも関係します。
第3章 返戻率が変わるポイントと、FPが見たおすすめ商品

学資保険の返戻率は、同じ商品でも契約条件で大きく変わります。
たとえば、若く始めるほど有利です。0歳で加入する場合と5歳で加入する場合では、0歳で加入した方が返戻率が高く、数%違うこともあります。
また、払込期間が短いほど返戻率は高く、祝い金を途中で受け取るプランを選ぶと、その分返戻率は下がります。
特約を付けすぎると、純粋な貯蓄部分が減るため、返戻率も低下します。
まとめると、学資保険の返戻率を高めるポイントは、「早く始めること」「早く払い終えること」、また「特約を付けないこと」です。子どもが小さいうちに始め、短めの払込期間を選ぶほど、保険会社が運用できる時間が長くなり、結果的に返戻率も上がりやすくなります。
おすすめ学資保険(2025年10月現在)
特徴:「S型(ステップ)」と「J型(ジャンプ)」の2種類の受け取り方法がある。兄弟割引制度もあり。
メリット:返戻率が高く(最大約109.5%)、短期払込も選べる。契約者に万一があっても教育資金が確保できる安心設計。
デメリット:短期払込を選ぶと月々の負担が重い。中途解約時は元本割れリスクあり。
特徴:「こども祝金なし型」と「こども祝金あり型」が選べる。契約者死亡時の払込免除付き。
メリット:大手で信頼性が高く、サポート体制も安心。大学入学以降の資金準備に適している。
デメリット:祝金付きプランは返戻率が低下しやすい。加入時期が遅いと有利な条件になりにくい。
特徴:地域共済型で、教育資金に特化したプラン。受取りは、進学時期に合わせて中学・高校・大学プランから選択可能。
メリット:高い貯蓄性と保証のバランスが良い。
デメリット:設計自由度がやや低く、条件によっては返戻率100%を下回る可能性がある。
特徴:高校入学時に一時金、大学4年間は学資年金を受け取る設計。出生予定日の140日前から加入可能。
メリット:教育費が最もかかる高校~大学時期に備えられる。払込免除付きで安心。
デメリット:中学校など早期に資金が必要な場合には不向き。
特徴:貯蓄型重視で、大学進学時から年に1回、4回分割で受け取り可。10年払済・15年払済など短期払込を選べる。
メリット:返戻率が高め(最大約129.2%)で、シンプルな設計。大学進学資金を明確に準備できる。
デメリット:中学・高校入学時の資金準備には不向き。短期払込を選ぶと月額負担が重くなる。
これらはいずれも返戻率が105〜109%前後と安定しており、特に早期加入・短期払いを選ぶと有利になります。

学資保険は「どれを選ぶか」も大切ですが、「いつ・どう払うか」で結果がかなり変わります。0歳で始めた方と5歳で始めた方では、受取額に数万円〜十数万円の差が出るケースも出てきます。その意味では、早めの行動が一番の節約になりますね。
学資保険は「リスクを抑えたい人」や「確実に貯めたい人」にとって安心度が高い選択肢。「投資は怖いけど、少しでも増やしたい」という方は、学資保険を検討してみるのも良いと思いますよ。
第4章 FPが勧める「現実的で安心な貯め方」

「投資は怖い。でも、少しでもお金を増やしたい。」
そう感じる方はとても多いです。実は、学資保険とNISAを組み合わせるのも選択肢の一つです。
たとえば、月3万円の教育資金を用意するなら、
- 2万円をNISA(つみたて投資)
- 1万円を学資保険(保障付きの貯蓄)
というように分けると、リスクを抑えながら資産を増やせます。
大切なのは、「どれだけ増えるか」ではなく「続けられる仕組み」にすること。
最初から完璧を目指さなくても大丈夫。コツコツ積み立てるだけで、10年後・15年後に大きな安心感が得られます。

教育資金は“早く始めた人が勝ち”です。小さくてもいいので、夫婦で「今できること」からスタートしましょう。
もし「我が家にはどんな貯め方が合ってるんだろう?」と感じたら、一度専門家に相談してみてください。
Sweet Colorでは、婚活だけでなく「お金の未来設計」も一緒に考えるFP相談も行っています。



