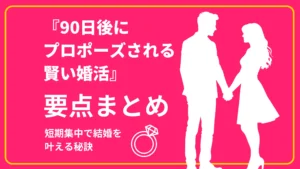児童手当が高校生まで拡大!FPが最新制度を徹底解説

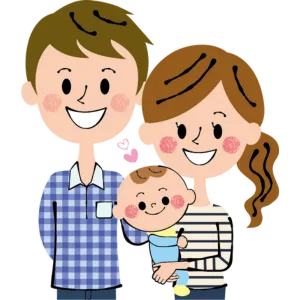
児童手当が気になるご夫婦
「児童手当っていくらもらえるのかな? それに何歳までもらえるの? 申請方法も知りたいな」
そんな疑問に答えます。
子どもが生まれると、ベビー用品・医療費・保育料など出費が増えがち。制度の変更も多いので「知らないまま損をしたらどうしよう…」と不安になる方は少なくありません。
児童手当は支給対象が高校生年代(18歳の年度末)まで拡大し、支給時期も年6回に変更しています。
最新制度でわかる「児童手当」:対象年齢・支給額・支給時期・申請の流れと、FPが教えるムダなく貯める実践術
この記事では、0歳〜高校生年代(18歳の年度末)までが対象となった最新の児童手当について、支給額、偶数月に支給というスケジュール、出生・転入から15日以内の申請など、児童手当のポイントを整理して解説します。
さらに、FPの視点で「児童手当を教育費へムダなく回す仕組み化」—専用口座づくり・定期積立・新NISA/学資保険との使い分け・第3子以降の加算を活かした家計設計—まで、今日から実践できる具体策をご紹介します。
私は埼玉県川越市にあるIBJ加盟の結婚相談所『マリッジコンシェルジュ Sweet Color』で活動する、FP2級資格を持つ婚活カウンセラーです。
成婚退会された会員さまからは、妊娠・出産・保育園入園・小中高進学といったライフイベントについてご相談をいただくことも多く、ご成婚後の人生設計まで伴走するサポートを行っています。
この記事では、「わが家はいくら・いつ・どう受け取れるか」がスッと理解でき、申請漏れ・手続きミスを防ぎながら、受け取った手当を将来の教育費に確実に変える方法まで一気に把握できます。結果として、出産前後の不安が和らぎ、夫婦で前向きに子育てマネープランを描けるようになります。
目次
第1章 「児童手当っていくらもらえるの?」最新制度をやさしく解説

「児童手当って中学生までじゃなかった?」と思われた方も多いでしょう。 2024年度の制度改正により、支給対象は高校生年代(18歳の年度末)までに拡大されました。 つまり、子どもが高校を卒業する年の3月31日まで、児童手当を受け取れるようになったのです。
支給額は年齢と子どもの人数によって異なります。 0歳から3歳までは月15,000円、3歳から18歳までは月10,000円。 第3子以降は0歳から18歳まで月30,000円と手厚い支援です。 支給時期も偶数月(2・4・6・8・10・12月)に変更され、2か月分をまとめて振り込まれる形になっています。
支給日は毎月15日ですが、土日や祝日にあたる場合は直前の平日に前倒しで振り込まれます。 この制度によって、定期的な入金サイクルが生まれ、家計の見通しが立てやすくなったという声も多く聞かれます。特に教育資金の積み立てに活用しているご家庭も増えています。

高校生まで対象が広がったのは助かりますよね。 特に3人以上のお子さんがいるご家庭では、18歳まで毎月3万円の支給を受けられることもあり、教育費の負担をぐっと軽くしてくれる制度だと感じます。
第2章 申請手続きの落とし穴とスムーズに受け取るコツ

児童手当は「自動的にもらえるお金」ではありません。 申請を忘れると、その月分は受け取れなくなることもあります。 出生届を出したあと、15日以内に自治体で申請が必要です。
また、転勤や引っ越しをした場合も再申請が必要です。 転出・転入のタイミングで一時的に支給が止まることもあるので注意が必要です。 公務員の方は勤務先への申請になる点も忘れずに確認しましょう。
児童手当を申請するときには、いくつかの書類が必要です。役所に行く前に、あらかじめ準備しておくと手続きがスムーズです。 主な必要書類は次のとおりです。
- 児童手当 認定請求書
- 請求者の健康保険資格を証明する書類(資格確認書・資格情報のお知らせ など)
- 請求者名義の振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 請求者と配偶者の個人番号確認書類および身元確認書類
これらをそろえて、市区町村の窓口で「児童手当の申請をしたい」と伝えれば、担当の方が丁寧に案内してくれます。 申請が遅れると受給開始が翌月になることもあるため、出生届や転入届と同時に手続きを済ませるのがおすすめです。

「手続きが面倒で後回しにしていたら、支給が翌月になってしまった…」という方も多いんです。出生届と同じタイミングで済ませましょう。
第3章:FPが教える「児童手当を教育費へムダなく回す仕組み化」

児童手当は、子育て世帯にとって「2ヶ月に一度必ず入るありがたいお金」です。 ただ、生活費の口座にそのまま入ってしまうと、気づかないうちに日常の出費に消えてしまうことも。 そこで大切なのは、“児童手当を教育費へ確実に回す仕組み”を作ることです。
① 専用口座をつくる:お金の「行き先」を決めておく
まず最初におすすめしたいのが、児童手当専用の貯蓄口座を用意することです。 メイン口座と分けるだけで、「使ってはいけないお金」という意識が自然に生まれます。 支給されたらすぐに自動振替設定をしておけば、手動で移す手間もなく続けられます。

児童手当って「いつの間にか使ってしまう」ご家庭も多いんですよね。もらったらすぐ別口座に移す。それだけで貯め体質になります。
② 定期積立にする:ムリなくコツコツ貯まる仕組みを作る
次に、定期積立(自動積立)を活用しましょう。 たとえば児童手当の振込口座から月1万円ずつ自動で積み立てる設定にしておけば、「貯める習慣」が勝手に続く状態になります。 児童手当の支給額(1人あたり月1万円〜1.5万円)を基準にすれば、無理なく教育費に充てられます。
高校卒業までに受け取る児童手当の総額は、約234万円(※1人目の場合)。 これを全額しっかり貯められれば、大学入学時のまとまった資金として非常に心強いです。
③ 新NISAを活用:長期・分散・非課税で増やす
「ただ貯めるだけではもったいない」と感じる方には、新NISAでの運用もおすすめです。 児童手当をそのままNISA口座で投資信託に積み立てれば、非課税で効率的に増やすことが可能です。 運用期間が10年以上あれば、短期の値動きリスクも抑えられ、長期的な教育資金形成に向いています。
例えば、児童手当のうち月1万円を新NISAで積み立て、年利3%で15年間運用すると約230万円が約300万円に。 リスクを取りすぎず、しっかり増やすことができます。
④ 学資保険との使い分け:安全重視ならこちらも◎
「投資はちょっと不安…」という方には、学資保険が安心です。 満期時に高校・大学入学金として受け取れるよう設計されているため、目的が明確で、教育費を確実に準備できます。 途中解約のデメリットだけ理解しておけば、リスクを抑えた堅実な選択になります。
⑤ 第3子以降の加算を活かす:家計全体の見直しチャンス
第3子以降は児童手当が月3万円と大幅アップ。 この差額分を「生活費に使わずに全額貯蓄」するだけで、家計にゆとりが生まれます。 教育費や住宅ローンの繰り上げ返済に回すのも有効です。
また、子どもの成長に合わせて保険や家計全体を見直すタイミングでもあります。 児童手当の使い道をきっかけに、ライフプラン全体を整理してみましょう。

児童手当は“もらって終わり”ではなく、“未来を育てるお金”。仕組みを作っておけば、家計が自然と整い、安心して子育てできます。
第4章 将来の安心につなげるために:制度を知ることが“最初の一歩”

婚活中や結婚を控える方の中には、「子育てにどれくらいお金がかかるの?」という不安を感じる方がたくさんいます。 でも、児童手当のような制度を知っておくだけで、未来の見通しはぐっと明るくなります。
出産・育児は想像以上にお金が動く時期。 だからこそ、「もらえるお金」を最大限に活かすことが大切です。 手当の申請・管理・貯蓄の流れを一度仕組み化しておけば、将来の教育費も安心です。

婚活中から“制度を知る力”を持っている人は、結婚後も強いです。お金の話ができるパートナーは、信頼されやすいですよ。
結婚や出産をきっかけに、「お金の流れを見直す」ことは家族にとって大きな意味があります。 今回の記事をきっかけに、ぜひ児童手当を「もらうだけ」ではなく、「未来を育てるお金」として活かしていきましょう。